お月見は、日本の伝統的な行事の一つで、毎年9月に行われます。お月見の日には、満月が美しい夜空を飾り、家族や友人が集まってお団子や団栗、柚子などの秋の味覚を楽しむことが一般的です。
お月見の起源は、中国の秋の収穫祭である中秋節に由来しており、日本では古くから農事の神様である月読命(つくよのみこと)を祀る行事として行われてきました。月は古代から日本人にとって特別な存在であり、お月見はその月の神々への感謝を表すものでもあります。
お月見の際には、月を見上げながらお供えをすることが一般的です。また、月見団子を食べることも欠かせない行事となっています。その他、笹の葉で作ったつき桃を吊るしたり、お供え物として柚子や団栗を飾るなど、様々な風習があります。
現代では、お月見は家族や友人と楽しむ行事として親しまれており、特に夜の公園や庭で月を眺めながら団子を食べることが一般的です。お月見を通じて、季節の移り変わりや自然との調和を感じることができ、日本の文化や風習を体験する良い機会となっています。
もっと見る ▼
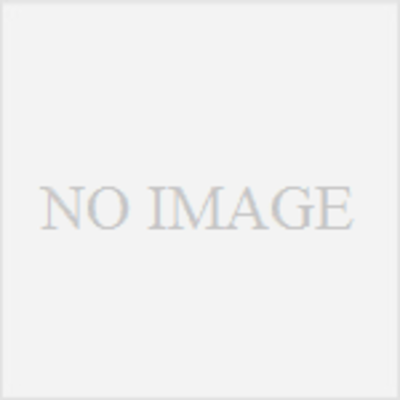
 「お気に入り」を解除
「お気に入り」に追加
「お気に入り」を解除
「お気に入り」に追加