お月見は、古来より日本で行われてきた風物詩の一つで、秋の夜、満月を眺めながら月を愛でる行事です。お月見の起源は、中国の秋の祭りである中秋節に由来しており、日本では平安時代から行われてきました。
お月見の主な行事としては、つきみを楽しむことや、団子を食べることが挙げられます。お月見の夜には、家族や友人たちと一緒に庭や公園などで月を眺めながら、団子や栗などの秋の味覚を楽しむことが一般的です。
また、お月見の際には、お供え物や灯籠などを飾り、月明かりの下でお団子を頂く風習があります。お団子は、満月をイメージして丸い形をしており、一般的には白い団子(白玉団子)が食べられます。
お月見には、月が美しい秋の夜を楽しむという意味のほか、家族や友人との絆を深める場としても重要な意味があります。お月見の日には、月の下でのんびりと過ごす時間が大切にされ、日本の伝統行事として親しまれています。
もっと見る ▼
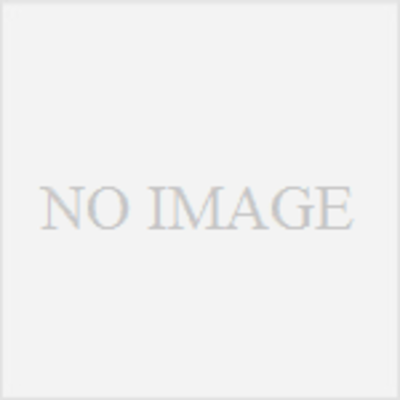
 「お気に入り」を解除
「お気に入り」に追加
「お気に入り」を解除
「お気に入り」に追加